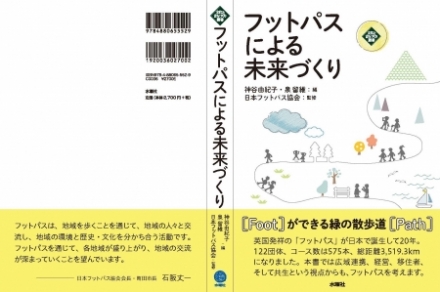- 執筆者: izumi
- コメント: 0
2024年地域通貨稼働状況調査の結果について
例年実施している地域通貨の稼働調査の結果(速報版)を公開します。この調査は、日本の地域通貨の稼働状況を把握するために、泉留維(専修大学経済学部教授)と中里裕美(明治大学情報コミュニケーション学部教授)が定期的に実施しているものです。今回の調査では2024年12月時点で184の稼働中の地域通貨を確認しました。なお、今年は、24年末に実施した質問紙調査(稼働中の全地域通貨対象:速報的な論文としては「2024年全国調査から見えてきた日本の地域通貨像」)の結果等を反映さえ、過去に遡って数値などの見直しを行っています。詳しくは、ファイルをご覧ください。なお、今年度は速報版のみ公開となります。