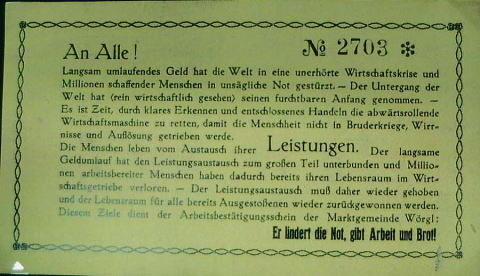- タグ:
- 執筆者: izumi
- コメント: 0
財産区悉皆調査の結果などについて
財産区悉皆調査の結果などについて(2011年9月29日)
文部科学省の科学研究費補助金・特定領域研究『持続可能な発展の重層的環境ガバナンス』(領域代表者:植田和弘・京都大学大学院教授)の「グローバル時代のローカル・コモンズの管理」班 (研究代表者:室田武・同志社大学教授)の一事業として実施されていた財産区悉皆調査(実施責任者:泉留維・専修大学准教授)ですが、2008年3月31 日付けで結果をとりまとめた報告書を発行し、その後データの点検や内容の充実を図り、2011年8月3日付で『コモンズと地方自治:財産区の過去・現在・ 未来』という本を発刊しました。これもひとえに自治体関係者の皆様のご協力の結果であり、関係各位には厚く御礼申し上げます。
調査結果の概要
対 象:全市区町村(1827自治体:1804市町村、23特別区)
方 法:質問紙郵送方式(2007年3月1日付送付)
質 問:2007年(平成19)年3月31日時点での財産区の状況など
①回答自治体数:1,795(98.3%)
②財産区保有自治体数:442(24.2%)
③設置されている財産区数:3,704
④平成の大合併期間に解散した財産区数:56
⑤平成の大合併期間に新設された財産区数:55
⑥平成の大合併期間に合併した財産区数:2
報告書のダウンロード
『財産区悉皆調査報告書:ローカル・コモンズとしての財産区』(PDF・1.8MB)
<「資料編Ⅲ章 財産区一覧」(エクセル・532KB)>
☆運営中の財産区(平成19年3月末時点)については、ここで詳細なデータベース検索を行うことができます。
なお、報告書のデータ等にミスが見つかっていますので、可能でしたら、下記の著書をお読みいただければ幸いです。
『コモンズと地方自治』について
著 者:泉 留維, 齋藤 暖生, 浅井 美香, 山下 詠子
出版社:日本林業調査会
価 格:2500円
目次などの詳細については、日本林業調査会のHPをご参照ください。
 湯川第一共同浴場
湯川第一共同浴場 新和田湯会館
新和田湯会館 新井の湯
新井の湯 浅尾原財産区会館
浅尾原財産区会館 学術論文や雑誌記事の一部は、
学術論文や雑誌記事の一部は、