桜が散り間際、鎌倉市に赴き、里道の散策をしました。鎌倉市は、言わずもがなですが、「古都保存法」を誕生させた市でもあり、環境保全を取り組む先駆的な自治体ですが、そもそもは住民の反対運動から政策につながっていくというパターンが観察されます。

財団法人鎌倉風致保存会の事務所建物。ハーフティンバーと呼ばれる独特な妻壁を持つ旧安保小児科医院の建物。

御谷(おやつ)騒動のモニュメント。鶴岡八幡宮の裏山である御谷(御谷戸が縮まったらしい)の宅地開発に反対する運動で、大佛次郎などが運動の母体として作ったのが財団法人鎌倉風致保存会(1964年設立)である。1966年、日本のナショナル・トラスト第1号と言われる御谷山林(1.5ha)を買収し、現在のような光景を保っています。フェンスで覆われて、クローズド・スペースになっているのが若干気になるところです。

広町緑地には、江ノ電七里ヶ浜駅から歩いて入りました。駅からの案内図がないためかなり迷って正規の入り口ではないと思われる日蓮宗霊光寺の裏山からでした。写真は七里ヶ浜小学校近くにある出入り口付近の尾根から撮ったもの。緑地のすぐそばまで住宅地がびっしり詰まっています。

とても手入れがされた里道(自称「もののふの道」)です。

七里ヶ浜出入り口付近に過かがられていた緑地内の地図。残念なことに支柱から落ちていました・・・

里道を歩いて里山を降りると、谷戸が広がっています。耕作放棄されたかなり年月がたっているのか、水路はほとんど埋まり湿地のようになっていました。ただ、里道の方はしっかり整備され、木の橋も架けられています。

耕作放棄された水田も市の支援を受けて復興しようとしているようです。やはり元の自然を取り戻すためには、長年関わってきたヒトの営みの部分も取り戻して行かなくてはいけません。イングランドでは、すでに羊がいなくなったコモンに羊の放牧をわざわざ行って、風景(ランドスケープ)を保全しようとしています。














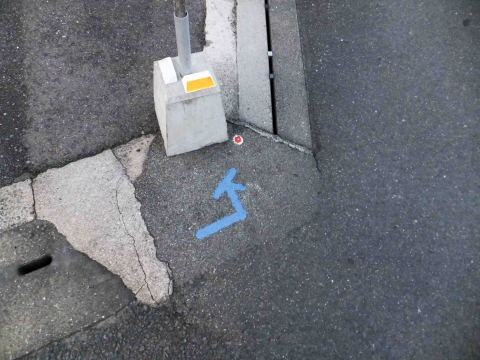

































 rido
rido