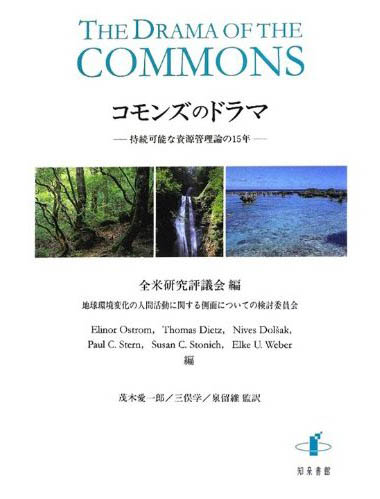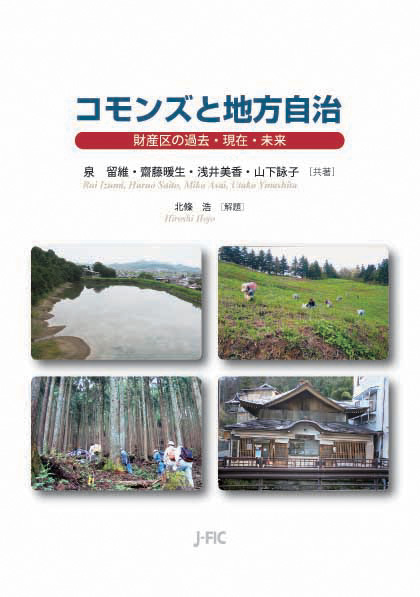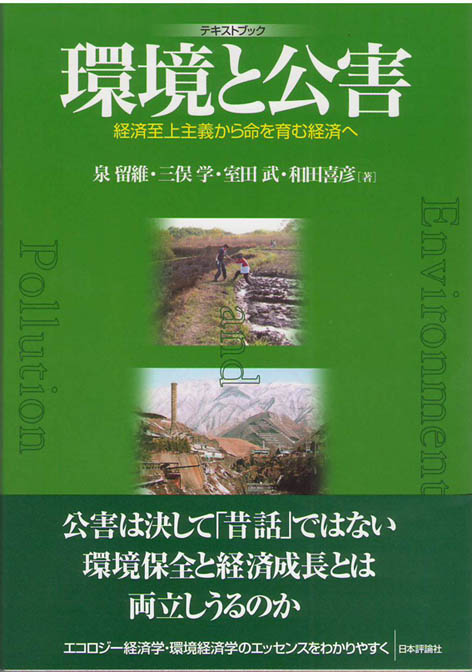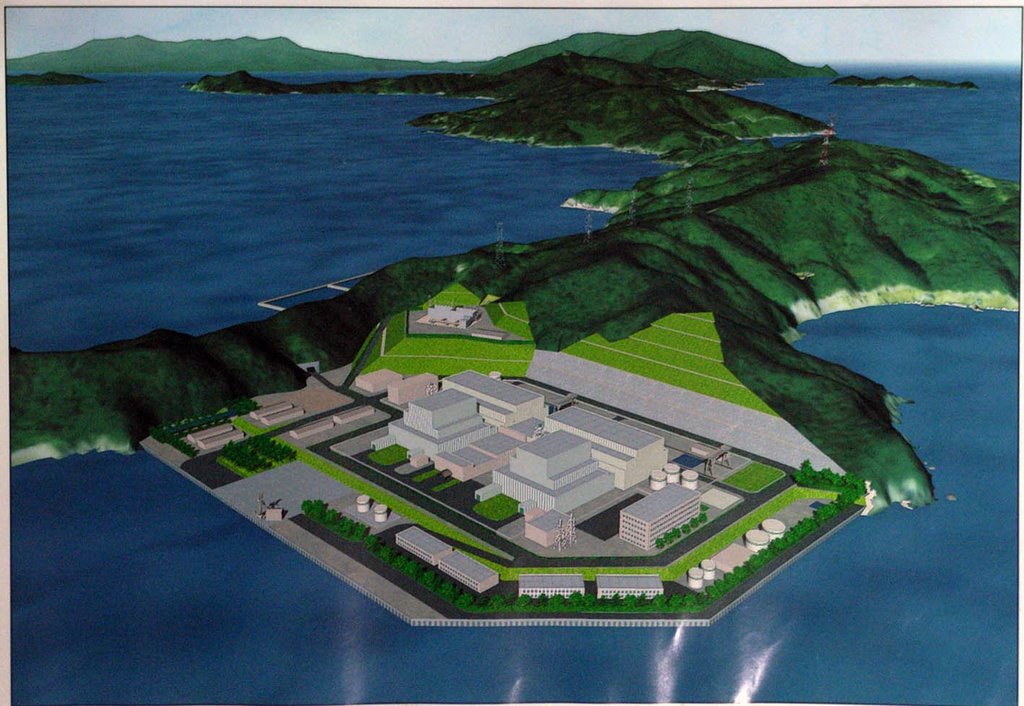「支え合いの仕組みから考える持続可能なコミュニティ」
ながらくコミュニティの紐帯を新たに作り出すためにタイムバンク導入を推進されてきたヘロン久保田さんをお招きして、持続可能なコミュニティ構築のための仕組みについて考えていきたいと思います。
■日 時 2010年6月12日(土)14:00~17:30(開場13:45)
■会 場 専修大学神田キャンパス・1号館4階 ゼミ44教室<変更しました>
千代田区神田神保町3-8
地下鉄九段下駅 出口5より徒歩3分、
神保町駅出口A2より徒歩3分、
JR水道橋駅西口より徒歩7分
地図 http://www.senshu-u.ac.jp/koho/campus/index06a.html
構内 http://www.senshu-u.ac.jp/koho/campus/index06b.html
■講 演 ヘロン久保田雅子さん「お金で買えない貴重な時間:時代を変えるためのタイムバンク」(60分)
村山和彦さん「都市計画のツールとしての”ピーナッツ”」(40分)
森野 榮一さん「持続可能なコミュニティとは?」(40分)
■参加費 資料代として700円
■主 催 ゲゼル研究会( http://grsj.org/ )
■問合せ 泉留維まで
メール rui.izumi at gmail.com (atを@に変更してメールをお送りください)
※どなたでもご参加いただけます。
小規模な部屋で開催を予定していますので、参加される方はメールでご一報いただけると助かります。なお、講演会終了後の懇親会に参加される方は、できるかぎり事前にメールでご連絡ください。
【講師プロフィール】
ヘロン久保田雅子
米国タイムバンク・エリア代表、フロリダ・インターナショナル・大学(FIU)講師。著書は、『この世の中に役に立たない人はいない』(創風社 2002)、『お金で買えない貴重な時間』(Time Banks USA 2010)など多数。1990年代初めより、コミュニティにおける新たな相互扶助構築のためにタイムバンク導入を推進している。
村山和彦
(株)みんなのまち代表取締役社長、都市計画・まちづくりコンサルタント。著書は、『地域通貨の可能性-「ピーナッツ実践報告」』(千葉まちづくりサポートセンター、2001)など多数。地域通貨ピーナッツの生みの親であり、コミュニティービジネスとしての地域通貨導入を推進している。
森野 榮一
経済評論家、ゲゼル研究会代表。WAT清算システム会員。著書、論文は『消費税完璧マニュアル』『商店・小売店のための消費税対策』(ぱる出版)、『エンデの遺言』、『エンデの警鐘』(共著、NHK出版)、『なるほど地域通貨ナビ』(編著、北斗出版) など多数。1999年、NHK BS1特集「エンデの遺言」の番組制作に参加・監修。その後、町づくりのアドバイスや地域通貨の普及活動に努めている。