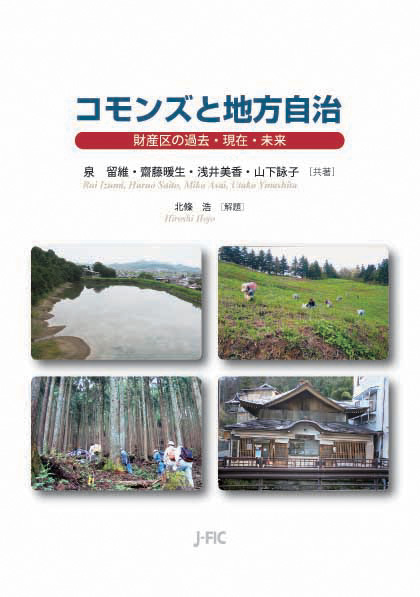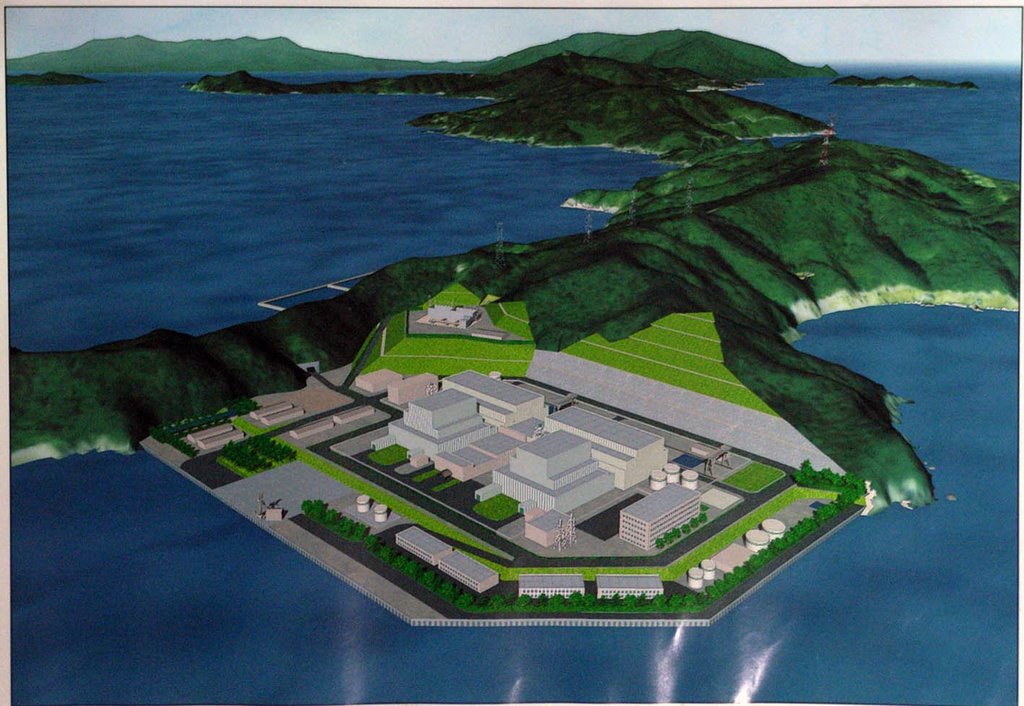- タグ:
- 執筆者: izumi
- コメント: 0
『コモンズと地方自治:財産区の過去・現在・未来』発刊
2011年8月、ここ4年来、研究を続けてきた財産区の研究成果が、本(『コモンズと地方自治:財産区の過去・現在・未来』)となりました。その多くが入会(いりあい)である財産区は、日本を代表するコモンズと言えるでしょうが、その包括的な現状は必ずしもわかっていませんでした。特別地方公共団体でもあるので、総務省が把握していても良いのですが、総務省は簡単な調査をするだけで、それほど多くの情報は持っていません。そのため、チームを組んで悉皆調査を行い、98%の財産区の状況をまとめ、分析したものが今回、本になっています。調査の概要については、ここをご覧ください。また、本の目次などの詳細は、発行元の日本林業調査会のHPでご確認ください。