韃靼旅行記(8):VWの工場と旅の終わり 2002-03-30 初出『人間の経済』36号 ゲゼル研究会
泉留維(いずみるい)
吉林で一泊し、翌日旅の起点とも言える長春に戻ることとなった。旅の終わりに徐々に近づいていくのが寂しかった。やっと中国の東北地方の雰囲気が感じ取れ始めたのに、という思いが湧き出ていた。しかし、長春にもどれば、もう1泊したら北京に戻らないといけないのだ。
吉林と長春はほんの100キロぐらいしか離れていない。この厳冬期でも慣れたドライバーなら1時間強で着く。私たち一行も優秀なドライバーがいて大変ありがたかった。そのドライバーは、同行した林さんの朋友である王さんであり、彼が運転している車は、フォルクスワーゲン(以下VWと表記)のジェッタ(Jetta)である。このジェッタは、長春市では石を投げれば必ず当たるというほどありふれた車である。その理由は、長春市には、VWの合弁工場があるからである。中国人は一般に日本車への評価は高い、ただ長春市はVWの工場があり、あちこちにディーラーがいて修理屋も多く、そのため自然と多くの人がVW、特にお買い得なジェッタを購入する。市内のタクシーはほとんどと言っていいほど赤のジェッタである。
この合弁会社は、1990年に設立された中国最大の自動車メーカーであり、第一汽車集団とVWがつくったということで会社名は「一汽VW」である。長春市の郊外の一角は、自動車に関する様々な工場や労働者の住宅からなる壮大な基地となっている。長春市の幹部の口利きで、一汽VWのラインを見学することができることになった。自動車のラインはテレビでしか見たことがなく、非常に興味津々であった。
昼過ぎにラインがある敷地へと向かったが、出入り口である門は非常に警備が厳重であった。昨日行ったダムの比ではない。市の公用車で行ったのであるが、それでもしっかりトランクまでチェックされ、やっと敷地に入り見学ができるラインのある建物に行けた。わたしが訪れたラインは、アウディのA6とVWのジェッタのラインであった。ラインの全長は2,000メートル、年間にジェッタが16万台、A6が3万6000台生産され、ほぼすべて国内で販売されるそうだ。部品は、80%が国内調達だが、ただエンジンは完全輸入のようである。私たちが見ることができたのはほんの一部であり、写真を撮ってはいけなく、ただ歩いて眺めることとなったが、あちこちにドイツ語で説明書きがあり、ちらほらとドイツ人の技師がいて、一般労働者を見なければ整然としたドイツの工場である。それにしても、車の組み立て作業は壮観だ。一台の車を作るために、膨大な部品と組み立て工程が必要であり、国家が力を入れて支援する産業であることをうなずける。この産業は、大きな雇用を生み出すのである。
ライン見学の最後にVWの中国での次期主力車「ボーラ」が展示してあった。一汽VWが最近生産を始めた小型乗用車「ボーラ」(排気量1,600〜1,800cc)は、VWが欧州や日本などで販売している主力セダンである。中国での販売価格は、17〜23万元(1元=16円、約270〜370万円)に設定されている。
敷地から出るときも、門で再びトランクまで調べられた。どうも、中国における最新の技術が使われた部品などが敷地外に持ち出されるのを防ぐためのようである。産業スパイも横行しているのであろう。
一汽VWのラインを見た後は、次に第一汽車集団が作っている車の展示施設へと向かった。毛沢東や周恩来などといった数々の中国の指導者を乗せてきた中国国産の要人用高級車「紅旗」が展示されていた。今年初め「紅旗」がフルモデルチェンジされて新しくできた「大紅旗」が中央に陣取っている。排気量4,600cc、長さ約5.5メートルの堂々たる車体であり、展示場でもひときわ目立っていた。ただ、やはりエンジンをつくる技術はまだなく、「紅旗」の主な車種のエンジンは、すべて日本の日産製である。ただ、この車は、中国の威信をかけた車であることには変わりなく、常に要人を乗せて走っている。
自動車の生産基地を見学し、夕刻にさしかかったころには私たちは長春空港にいた。北京に戻るためである。今回の東北地方の旅行は、とりあえずはここで終了である。クロテンの交易の1つである「山丹交易」の一端を見るために、中国東北部へと初めて足を運んだのであるが、それとは関係のない多くの人に出会い、歴史的文物を見、最先端の施設にふれることもできた。旅行とは、最初のねらいとは関係ないことが多々起きる。それが旅行の醍醐味でもあろう。山丹交易に関しては、それほど多くの資料を得ることはできなかったが、予定外のことが起き様々な体験ができ、ある意味では旅本来の目的が果たせたと言っても良いかもしれない。近々再び訪れるつもりでいる。再見了!
(完)
 朝8時に東武浅草駅を出発。最初の訪問地「藤岡町歴史資料館」にて渡良瀬遊水地と田中正造の話を聞いた後、遊水地に移動。
朝8時に東武浅草駅を出発。最初の訪問地「藤岡町歴史資料館」にて渡良瀬遊水地と田中正造の話を聞いた後、遊水地に移動。












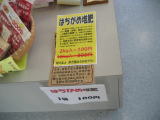
































 マン
マン









































































